 バリ島 観光 カーチャーター / キーワードで見るバリカルチャー
バリ島 観光 カーチャーター / キーワードで見るバリカルチャー

バリ島文化に関するキーワード!
バリ島の文化に興味のある方必見の、キーワードページです!バリ島の文化に関する様々な言葉を紹介しています。こちらのキーワードページから、初歩的なバリ島の文化を知ることができるでしょう。まずはこちらのページをご覧くださいませ!!
- メニュー & 料金

- 口コミ

 バリカルチャー AtoZ
バリカルチャー AtoZ
- A
-
アントニオ・ブランコ美術館 - Antonio Blanco Museum -
自ら「バリのダリ」と名乗っていた奇才の画家、ブランコ氏のミュージアムです。 アントニオ・ブランコ氏本人はすでに他界していますが、彼の息子であり、アート創作をしているマリオ・ブランコ氏によって運営されています。 ブランコ氏の邸宅を改築した洋館テイストのフロアには、バリ島を象徴するレゴンダンスの作品や、彼の孫を描いたものなど、1F~2Fに渡り多く展示されています。
-
アルマ美術館 - Arma Museum -
こちらもウブドを代表する美術館の1つです。 普通の美術館とはちょっと違っていて、絵画の常設展・特別展の他、演劇や絵画教室の開催、 ワークショップの企画、図書室、会議やセミナーの施設など、様々な使い方ができるミュージアムです。 また、敷地内にあるオープンステージでは、新月と満月にのみ公演されるケチャダンスがあり、迫力あるパフォーマンスで人気を博しています。
-
アートセンター - Art Center -
ヤングアーティストを育成するデンパサールの国立芸術大学。 そのすぐ近くに建つアートセンターは、広大な敷地の中に美術館・オープンステージなどが立ち並ぶバリ芸術の殿堂です。 毎年6月頃から1ヶ月間、アートセンターで開催されるバリ・アート・フェスティバルが有名で、国内外からアーティストが訪れます。 期間中は毎日日替わりで様々なパフォーマンス・イベントが行われ、大勢の人でにぎわいます。 併設される美術館では、伝統絵画や木彫り、銀細工などバリならではの美術品を観賞できるので、ぜひ訪ねてみましょう。
- B
-
バジェラ・サンディ - Bajera Sandi -
バジェラ・サンディはデンパサールの東、レノン地区にあります。 ここはバリ州の政庁舎や日本領事館など、政府管轄の建物が集まるビジネスエリア。 その中で美しいシルエットの塔がひときわ目を引くバジェラ・サンディは、外観は記念塔、内側は歴史博物館という構造になっており、比較的新しい観光スポットです。 木々が生い茂る広い公園を通って館内に入ると、古代から現代までの遷り変りがフィギュアで展示されており、バリの歴史に分かりやすく触れることができます。 2階には展望室もあり、そこからはデンパサールを一望する素晴らしい眺めを見ることができます!デンパサール観光に来たらぜひ寄ってみてください。
-
バリ博物館 - Bali Museum -
初めてバリに来る方の観光ツアーで高確率で組み込まれているのが「バリ博物館」。 これといって大きいわけでも派手な訳でもないんですが、じっくりバリ島のカルチャーを学ぶのにはピッタリです。 バリ風の建築様式の中に平屋の棟が立ち、歴史/宗教/生活 など、ジャンル毎にバリ島ならではの文化をご紹介しています。 日本語の案内は無いのでガイドさんと一緒に行くのがおすすめ。
-
バロン - Barong -
バロンはバリ・ヒンドゥーを語る上で欠かせない存在。 バリ・ヒンドゥーでは、人の心の中は常に善と悪が戦っており、決着が付くことはない=すなわち、この世には善悪が永久に存在する、と考えられています。 その「善」を象徴するシンボルが 聖獣バロン です。 また、「善と悪」以外にも、 「生と死」 「上と下」 「海と山」 のように、物事には対極にあるものが常に存在すると考えられているのがバリ・ヒンドゥーの特徴です。
-
バロンダンス - Barong Dance -
バロンダンスは、バリ・ヒンドゥーの象徴的存在 「聖獣バロン」と「魔女ランダ」 の果てしない戦いを描いた物語です。 サデワ王子、大臣、シワ神、死神、死神の弟子カレカなどの登場人物によって物語が進み、終盤でサデワ王子がバロンに、カレカがランダに変身して戦うシーンが見られます。 ダンスによっては、トランス状態に入ったダンサーがクリス(短剣)で自らの胸をさすクリスダンスも見ることができますよ。
-
バトゥアン村民家 - Batuan Private House -
バトゥアン村民家は、デンパサールから15kmのバトゥアン村にあります。 この民家は、バリ人の家族6人が普段の生活を送りながら住んでいるところで、お布施を払って中を見学することができます。 バリの中にある民家は、どこでも形が同じです。 建物の中の配置がすべて同じです。 東側にはお祭りのお供えものを作るための建物、南側には、台所があります。 西側にある建物は、親たちの部屋になります。 そして北側にある建物は、子どもたちの部屋、または出来たお供え物を置く建物になっています。 でも、バリ島のヒンズー教の家には、東北側に家族のお寺があります。 このお寺は“家族寺”と呼ばれ、毎日お供え物をし、お祈りをします。
-
バトゥアンスタイル - Batuan Style -
カマサン・スタイルと近代西洋の技法が融合した画法で、黒、白など暗いトーンで描かれた遠近感、立体感のない細密画が「バトゥアンスタイル」と呼ばれるものです。 ヒンドゥーの神話やバリのお祭り、稲刈り風景など、日常の様子がキャンバス全体に隙間無く描き込まれているのが特徴です。 このスタイルの絵画はアルマ美術館で観ることができますよ。
-
ブラフマ - Brahma -
バリヒンドゥーを知る上で絶対に欠かせない神様、3大神のひとり、ブラフマ。 神にはそれぞれ役割がありますが、ブラフマは世界の創造を司り、水鳥ハンサに乗った赤い肌の男性として表現されます。
- C
-
チャナン - Canang -
バリ島の道、家、寺院・・・いたるところで目にするのがこの小さなお供え物チャナンです。 バリ島といえばこれ!というイメージの方も多いと思います。 ヤシの葉で編まれた小さなお皿の中に、色とりどりの花たち。 この小さなお供え物をバリの女性たちは毎日神々に捧げます。 お花の色にもちゃんと意味があるんですよ。 チャナンに供える花の色は最低3色以上必要で、多いのが赤・ピンク・白 のパターンです。 この3つの色は、ヒンドゥーの三位一体の神様、シヴァ、ヴィシュヌ、ブラフマーを象徴しています。 そしてバリ・ヒンドゥーではさらにもう一つの神様がいて、これが サンヒャン・デウィ と呼ばれる最高神になります。 小さなお供え物の中にも色んな意味があって面白いですよね。 滞在中、チャナンを見かけたら何が入っているかぜひ見てみて下さいね。
- G
-
ガルンガン - Galungan -
ガルンガンはバリ島伝統の暦、ウク暦に基づくお祭りの中でもっとも大きなもので、210日周期で行われます。 神様が世界を創造し善が悪を滅ぼしたことを祝うためのもので、天上からバリ島に帰ってくる祖先の霊を盛大に迎えるお祭りです。 日本のお盆とほとんど同じ行事ですね。 ガルンガン前になると、バリの村々ではペンジョールと呼ばれる美しい竹飾りが通り沿いにずらっと並ぶ美しい風景を見ることができますよ。 ガルンガンは当日だけでなく、前後数日間も色々な儀式があり、明日は前夜祭にあたるPenampahan Galungan です。 この日はガルンガンを祝うための準備をする日で、家を清掃し、家の前には竹をヤシの葉作物、果物、稲、砂糖きびなどを吊るした ペンジョールを立てます。
- I
-
イムレック(中国旧正月) - Imlek(Chinese New Year) -
イムレック(中国旧正月)ヒンドゥーとは関係ありませんが、インドネシアやバリ島でも正式な祝日として認められています。 中国暦においてはお正月は1月1日ではなく、1月22日頃から2月19日ごろまでを毎年移動します。 中国や華人にとっては一年でもっとも重要な祝祭日で、旧正月から数日間は帰省をしたり、 日本と同じように子供にお年玉をあげたり、重要な取引先に贈り物をして日頃の感謝を表す文化があります。
- J
-
ジェゴグ - Jegog -
ダンスがメインではありませんが、バリ島西部のヌガラに伝わる伝統的な「ジェゴグ演奏」というものもあります。 ジェゴグは竹で作られた竹筒打楽器で、大小のジェゴグ14台で1楽団となります。 4音階の竹筒打楽器は世界でもこのジェゴグだけ。 4つの音階は東西南北の方位を意味し、それぞれに神が宿りその中心にシヴァ神があると言われています。 竹の音にもバリ・ヒンドゥー教の宇宙観が具現化されたバリならではの楽器です。
- K
-
カマサンスタイル - Kamasan Style -
バリ文化の中で忘れちゃいけないのが 『バリの絵画』。 ネカ美術館、アルマ美術館、プリルキサン美術館など、ウブドには1日で巡りきれないほど美術館があります。 バリの絵画には大きく分けて5つのスタイルがありますが、その中でもっとも古く、16世紀から伝わる伝統絵画が "カマサン・スタイル" と呼ばれるもの。 平面的で遠近感のない図柄が綿密に描かれているのが特徴で、マハーバーラタやラーマヤナなどのインド叙事詩を題材にしています。
-
クバヤ - Kebaya -
クバヤはバリ島の女性が着る伝統衣装。 ブラウスとロングスカートがセットになった衣装で華やかな色合いや豪華な刺繍が特徴。 バリの女性は祭礼の時には必ずこれを来て寺院に参拝をします。 クバヤはオーダーメイドで作る場合と既製品の中からサイズに合ったものを買う場合がありますが、自分のサイズぴったりに作るなら絶対オーダーメイドがおすすめ。 アリッツでは一日で出来るオーダーメイド・サービスを行っていますよ。
-
ケチャダンス - Kecak Dance -
バリ島3大舞踊のひとつ、ケチャダンス。 ダンス中のセリフは一切なく、数十人の上半身裸の男たちが 「ケチャケチャケチャ・・・」と合唱しながら円陣を作ります。 その中で、きらびやかなな衣装をまとったダンサー達がインド古代叙事詩「ラーマーヤナ」の物語を演じます。 バリ島でケチャダンスが公演されている場所はいくつもありますが、一番有名なのはウルワトゥ寺院のケチャダンス。 その次に人気があるのがタナロット寺院のケチャダンスです。
-
クニンガン - Kuningan -
ガルンガンが「バリ島の迎え盆」なのに対して、クニンガンは「バリ島の送り盆」にあたるお祭りです。 クニンガンはガルンガンの10日後・11日目に行われ、ご先祖様を天界に送り出すため、バリの人々は皆お寺に行き祈りを捧げます。 バリ・ヒンドゥー全ての神様が天界に帰る日とされ、ヒンドゥー教徒として、より賢明で良い人生を送ることを誓う日です。 ガルンガン同様、クニンガンの前後も、道路が渋滞したり、観光地やショップが一部お休みとなる事が多いので注意が必要です。 約7カ月に1回行われるガルンガン & クニンガンの時期にバリ島旅行に来られる方は、ぜひお祭りの様子や鮮やかに彩られたお寺にも注目してくださいね。
- L
-
レゴンダンス - Legong Dance -
バリ舞踊の中でもっともきらびやで優美なダンスがこちら。 ガムラン演奏に合わせて豪華な衣装に身を包んだ女性ダンサー達が踊ります。 レゴンダンスの中にも何十もの演目があり、有名なのは宮廷舞踊の「レゴン・クラトン」や、ラッサム王の物語を表現した「レゴン・ラッサム」、 華やかな極楽長が舞う様子を表現した「チェンドラワシ」など。 中には男性ダンサーが1人で踊るものもあります。 リズムカルで見た目にも美しいので、観客を飽きさせません。
-
ル・メイヨール博物館 - Le Mayeur Museum -
バリを愛したベルギー人画家、ル・メイヨールの旧邸宅 兼 博物館がサヌールにあります。 ル・メイヨールは1880年にブリュッセルで生まれ、1932年~1958年の間にバリ島に暮らしました。 彼のバリ人の妻でありモデルであるNi POLLOKを描いた数々の作品は、住んでいた家を改築した現在のル・メイヨール博物館で見る事ができます。 サヌールビーチ目の前にあるのでのんびり散歩がてら見に行ってみて下さい。
- N
-
ガベン - Ngaben -
お葬式をお祭りと言うのは日本の感覚では不謹慎な気がしますが、こちらでは「火葬」は人生最大のお祭りでもあります。 人が亡くなると埋葬して、ムプガット(mepegat)という「別れの儀礼」が行われます。 その後で改めて火葬が行われますが、火葬場へ向かう際には人々が長い行列を作り、 激しいガムラン音楽が鳴る中で、男たちが「バデ」と呼ぶ御輿と、牛の形をした火葬棺を担いで火葬場へ向かいます。 バデの形やお祭りの規模は、亡くなった方のカーストの地位や資産の度合いによって大きく変わるそうですよ。
-
ネカ美術館 - Neka Museum -
バリ島で一番見応えがある美術館といえば、ウブドのネカ美術館。 貯蔵枚数やジャンルの幅広さではピカ一です。 特にバリ絵画はカマサン・スタイル/ウブド・スタイル/バトゥアン・スタイル/ヤング・アーチスト といった、 バリ島今昔のあらゆる絵画方式を見る事ができてとても面白いですよ。 ウブド観光と合わせて訪れるのがおすすめ。 アート好きなら2時間程度時間を見ておきたい場所です。
-
ニュピ - Nyepi -
バリ島独特のお祭りといえば、一番先に挙がるのがニュピですよね。 これはサカ歴の新年にあたる日です。 古くから この時期に地獄の神「ヤマ」が悪霊の国を一掃するため、悪霊がバリ島に逃れてくると言い伝えられています。 この日は 「悪霊が去るのを瞑想して静かに待つ日」とされ、一切の外出と電気や火の使用を許されません。 観光客や外国人も例外でなく、この習慣にしたがわなければなりません。 空港、公共機関、会社はすべてクローズとなり、人々は家で静かに一日を過ごします。 バリ島で暮らす外国人はホテルを取ってホテル内で過ごしたり、ロンボク島などニュピのエリア外に行くパターンが多いようです。
-
ニュピ(バリの人々編) - Nyepi (Case of Balinese) -
ニュピはバリ・ヒンドゥーの中で最も重要な祭礼なので、人々はオゴオゴと呼ばれる張りぼて作りから始まり様々な儀式を行います。 ニュピの3~4日前には「ムラスティ」という儀式があり、各村のお寺から御物を海や川に運んで清めます。 前日はオゴオゴを担って練り歩き悪霊払いをし、当日は一歩も家の敷地から出ずに静かに瞑想して過ごします。
-
ニュピ(ツーリスト編) - Nyepi (Case of Tourist) -
ニュピは夜中00:00から翌日24日 の朝6:00 頃まで、外出禁止・騒音禁止・電力の使用禁止・火の使用禁止、となります。 ホテルも例外ではないので、この期間を挟んでバリ島のいらっしゃっる方は23日は外出不可となりますが、 ホテルの敷地内や建物内では自由に過ごせますし、ホテル内のレストランは営業しているのでご安心ください。 前日に飲み物やちょっとした軽食を買っておいて、当日は朝からプールサイドやお部屋でゆっくり過ごされるのがおすすめです。
- O
-
オゴオゴ - Ogoh-Ogoh -
ニュピの前日に行うバリ島の伝統行事「オゴオゴ」です。 日本で言う節分の豆まきに似ており、「鬼は外~福は内~」と言って豆をまく代わりに、鬼のモチーフを背負って街を練り歩き、最後には燃やして悪霊払いをします。 「オゴオゴ」はヌサドゥア、ジンバラン、クタなど各エリアで22日の6時~11時ごろまで行われ、デンパサールのオゴオゴが一番大きく見応えがあると言われています。
- P
-
ペンジョール - Penjor -
ガルンガンとクニンガンが終わってからもしばらく街並みを彩ってくれるのがペンジョール。 これは日本で言う「竹竿」で、ガルンガン前に各家の前に立てるのが習わしとなっています。 高さは3m~5mほどもあり、弓のように穂先がしなっていて、これは聖なるアグン山を模しているそうです。
-
プルニカハン - Pernikahan -
バリ人の男女が結婚する時に行われるお祭りです。 婚礼の儀はそのカップルにも寄りますが、大体男性の出身の村で2~4日かけて行われます。 婚礼の前日には男性が花嫁の村に花嫁を貰い受けに行く風習がありますが 、婚礼当日まで女性は男性の家に入ることは許されず、親戚の家など別の場所で祈りを捧げて心身を浄化します。 当日は早朝から着替えや準備が始まり、男性の実家や寺院などでお祈りをし、儀式の一環として芝居のようなものを行ったり、お互いにご飯を食べさせあったり・・ と様々な儀式を夕方まで行います。 招待客はフルーツや食べ物など簡単なプレゼントを持って好きな時間に男性の実家を訪れ、好きな時間に帰っていくというシステム。 この婚礼の儀にはバリらしい伝統文化がたっぷり詰まっているので、機会があればぜひ参加してみるといいですよ。
-
ポトンギギ - Potong Gigi -
バリの人々の成人式にあたるお祭りです。 ポトンは「落とす」、ギギは「歯」という意味で、「歯を削る」ことになります。 麻酔無しで犬歯を削るこの儀式を終えることで一人前の成人とみなされます。 この行事はお祭りでもあるので、主催者が費用を出して親戚一同を集め、盛大に行われるそうですよ。
-
プリ・ルキサン美術館 - Puri Lukisan Museum -
展示数の多さではネカ美術館についで2番目になるルキサン美術館。 ウブドの中心地・プリサレン王宮からも歩いて10分程度の距離です。 ゆったりした敷地内には、緑いっぱいのガーデンを囲むよう展示棟が建てられており、じゃらんじゃらん(お散歩)がてらフラっと立ち寄るのにもおすすめ。 気持ちの良いオープンテラスのカフェもあります。
- R
-
ランダ - Rangda -
ランダはバロンと対をなす存在で、善の象徴バロンに対して悪を象徴しています。 ランダはたとえバロンに倒されても必ず生まれ変わり、バロンと終わり無き戦いを続けるとされています。 また、ランダは基本的には悪の魔術しか使えませんが、誰かの温かい心に触れて良心に目覚めることが出来れば、人間を治癒する魔術も使えるとされています。
- S
-
サファリ - Safari -
バリ人男性の民族衣装と言えば、バジュ・サファリ。 帽子と長袖の上着と巻きスカートのようなものが三点セットになっているのが一般的です。 上着は学生服のように詰め襟になっており、意外と暑い・・らしいです。
-
サンヒャン・デウィ - Sanghyang Dewi -
サンヒャン・デウィは、バリ・ヒンドゥーの教義における最高神の名前です。 先日ご紹介したシヴァ神(水の神)、ヴィシュヌ神(土の神)、ブラフマ神(火の神)はヒンドゥー3大神(トゥリムルティ) としてサンヒャン・デウィの下に位置づけられています。 サンヒャン・デウィは唯一にして究極の信仰対象であり、寺院の祭りや種々の儀礼においても彼に対しての祈りが中心となっています。
-
サプッ - Saput -
バリ島の寺院やお祭りでよく見かける白黒チェックの布、サプッ。 これにも宗教的な意味があるんです。 前回書いたように、バリ・ヒンドゥーは生と死、善と悪のように相対する概念がベースとなっています。 同じように、この白には 再生・誕生・生 などのポジティブな意味、 黒には 破壊・悪・死 などのネガティブな意味があります。 この布は石像に巻かれたり、男性の正装時に巻かれたりしていますよ。
-
シヴァ - Siwa -
たぶん、3大神の中で日本で一番有名じゃないでしょうか? 日本ではシバ(湿婆) と呼ばれているシヴァ神です。 シヴァは世界の寿命が尽きた時、世界を破壊して次の世界創造に備える役目を担っています。 乗り物はナンディンと呼ばれる牛で、ナンディも神として崇拝されているため、シヴァを祀る寺院の前にはナンディが祀られていることもあります。 ちなみに、商売繁盛や学問の神様として知られているガネーシャは、このシヴァ神の子供なんですよ!
- T
-
トゥンペッ ランデップ - Tumpek Landep -
トンパッランデップは180日に1回行われる「全ての乗り物が安心・安全に動くように祈る日」。 やり方は場所によって色々ですが、ヒロチャンオフィスではマンクーと呼ばれるお坊さんに祈祷していただき、 全ての車・バイクのフロントに竹で作ったお守りをくくり付けて聖水で清めてもらいました。 デンパサール空港では飛行機にもこのお祭りをしているようですよ!
- U
-
ウブドスタイル - Ubud Style -
1930年代にオランダ人画家ルドルフ・ボネがバリ島に招かれ、 バリの若いアーティストたちにキャンバスや絵の具を与え、遠近法や陰影の付け方、日常の生活や風景をテーマにする事などを教えて生まれた新しいスタイル。 村人の生活をテーマに、細密であるが、遠近法や立体感をつける画法を取り入れています。
-
ウパチャラ - Upacara -
ウパチャラとは、お祭りのこと。 バリといえばバリ・ヒンドゥー独自の暦に基づいたお祭りの数々があります。 代表的なものでは、静寂の日と呼ばれるニュピ、ガルンガン、クニンガン、サラスワティ など。 その他に新月と満月の度にお祭りがあるし、寺院そろぞれに創立祭のようなものもあり、数え出したらきりがありません。 お祭りの日は仕事も休むのが当たり前(ちょっと困りますが)だったりします。
- W
-
ヴィシュヌ - Wisnu -
ヒンドゥーの神様、ヴィシュヌです。 ヴィシュヌは世界を維持・保護する役割を持ち 、一般的には、4本の腕を持ち、右にはチャクラム(円盤)と棍棒を、左にはパンチャジャナ(法螺貝)と蓮華を持つ男性の姿で表わされます。 そして乗り物はガルーダと呼ばれる鳥の王。 ガルーダは 「ガルーダ・インドネシア航空」 にも名前が使われていますよね。 バリ島ジンバランにあるGWKは、正式名称を「ガルーダ・ウィシュヌ・クンチャナ」 という自然公園で、 その中では石で造られた巨大なヴィシュヌ像とガルーダ像を見ることができますよ。
- Y
-
ヤング・アーティストスタイル - Young Artist Style -
1950年代にオランダ人画家アリー・ シュミットの影響を受けた若いアーティストたちが確立した画法。 今までのスタイルとは異なり、陰影をつけずに描かれた、画面全体に溢れる光と鮮やかな色使いが特徴です。 バリ島の農村生活や自然風景が好んで描かれます。
口コミ一覧
 カーチャーターメニュー
カーチャーターメニュー
-
 バイクチャーター
バイクチャーター
-
 バギー/ブルー
バギー/ブルー
-
 スズキ カリムン
スズキ カリムン
-
 トヨタ アパンザーG
トヨタ アパンザーG
-
 スズキ APV
スズキ APV
-
 トヨタ イノヴァV
トヨタ イノヴァV
-
 ホンダ CR-V
ホンダ CR-V
-
 イスズ エルフ・ショート
イスズ エルフ・ショート
-
 イスズ エルフ・ロング
イスズ エルフ・ロング
-
 トヨタ ハイエース
トヨタ ハイエース
-
 ハイエース特別仕様車
ハイエース特別仕様車
-
 中型バス
中型バス
-
 トヨタ アルファード
トヨタ アルファード
-
 トヨタ ヴェルファイア
トヨタ ヴェルファイア
-
 ベンツ E250クラスカブリオレ
ベンツ E250クラスカブリオレ
-
 BMW 4シリーズカブリオレ
BMW 4シリーズカブリオレ
-
 ベンツ SLKクラス
ベンツ SLKクラス
-
 ベンツ Eクラス
ベンツ Eクラス
-
 ベンツ Sクラス
ベンツ Sクラス
-
 クライスラー 300C
クライスラー 300C
-
 ハマー リムジン
ハマー リムジン
-
 警察エスコートサービスバリ
警察エスコートサービスバリ
-
 フェラーリ(空港送迎)
フェラーリ(空港送迎)
-
 空港送迎
空港送迎
-
 当社の中型車はココが違う
当社の中型車はココが違う
-
 タクシープラン
タクシープラン
-
 チャータープラン
チャータープラン
 ジャンルで選ぶ
ジャンルで選ぶ
 カーチャーターで行く
カーチャーターで行く
観光スポット
 口コミランキング
口コミランキング
 インフォメーション
インフォメーション
 ピックアップ
ピックアップ
-
フォーシーズンズ サヤン

最高峰のリゾート バリ島旅行では、ハイクラスなホテル滞在を満喫しましょう。フォーシーズンズ サヤンは、バリ島で最も贅沢なリゾートのひとつとして観光客を魅了します。ウブドの渓谷を流れる川のせせらぎに耳を傾けながら、ここが人気の観光地であることも忘れてしまいそうな…
-
メルキュール リゾート サヌール

穴場的ホテルでバカンス バリ島に観光に来たなら、日本人観光客が少ない穴場的スポットでのんびりするのもおススメ!メルキュール・リゾートはビーチまでたった200m!いつも西洋人のリピーターで賑わっているホテルです。サヌールのプライベートビーチはまるで天国!広大な敷…
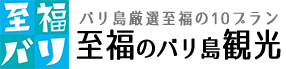

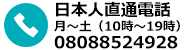
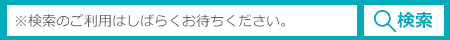
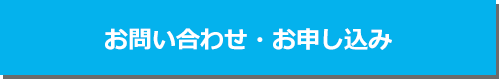
 からログインまたは会員登録をお願いします。
からログインまたは会員登録をお願いします。